
ゆうこです。 ゆうこです。年始に早々にタロー・デ・パリ®のお師匠さんの美香さんに、今年の流れについて見てもらいました。すると、「今年は集大成の年になるよー」と言われました。さらに、好きな占い師さんのYouTubeをみていたら「今年は集大成の年だよ」と言っていました。どう転んでも、「集大成の年」になるみたいですよ(^ ^)
先日、みんとしょたうに市内のフリースクルーの子どもさんをお招きして、ストーリーテリングのお話会をしました。
指導員さんの話によると、どうも普段はあまり自分から本を読もうとする機会は少ない様子でした。しかし、「ストーリテリングで聞いた話の内容を楽しく話しながら帰りました。こんな楽しみ方があるんだ。また、機会あれば是非」と引率の指導員さんの感想も含めてご報告くださいました。
これも読書。
「自分で本を読む読書」はハードルが高いため積極的にはしないかもしれません。でもそれは「イコール本嫌い」というわけではなく、形をかえれば読書も楽しめます。どんな形であれ、本に触れ、言葉に触れる機会を作っていくことは大切ことだなと感じた出来事でした。
また、やりたい。ぜひやりたい。子どこさん向けのお話会を。うちの子どもさんたちにも〜とご希望があれがお声がけくださいませ。
さて、本題に。
これまで「考える力」を中心に記事をお伝えをしてきました。
よければ過去記事↓を読んでみてください。
なぜ「考える力」にこだわっているかというと、私のメインの仕事「発達支援教室 まなび舎ぽっと」では、「考える力」を運動発達の側面と認知活動の側面で捉え、個々に合わせたプログラムを提供しているからです。身体レベルについては、みどりさんの記事で触れられることが多いので、私は認知レベル側をお伝えできたらと考えています。
認知レベルの考え方の柱は【フォイヤーシュタイン・メソッド】です。これは人の認知活動(情報を得て〜考えをまとめて〜行動に移す過程)をイスラエルのルーヴェン・フォイヤーシュタイン博士が自らの実践を理論に体系化したものです。フォイヤーシュタイン・メソッドに出会った時は、目から鱗がぽろりと落ちた感覚でした。なんと只今、日本の教育界に旋風を巻き起こしている”今井むつみさん”が同じような考えを提唱されていて、首がもげるくらい頷きながら本を読みました。
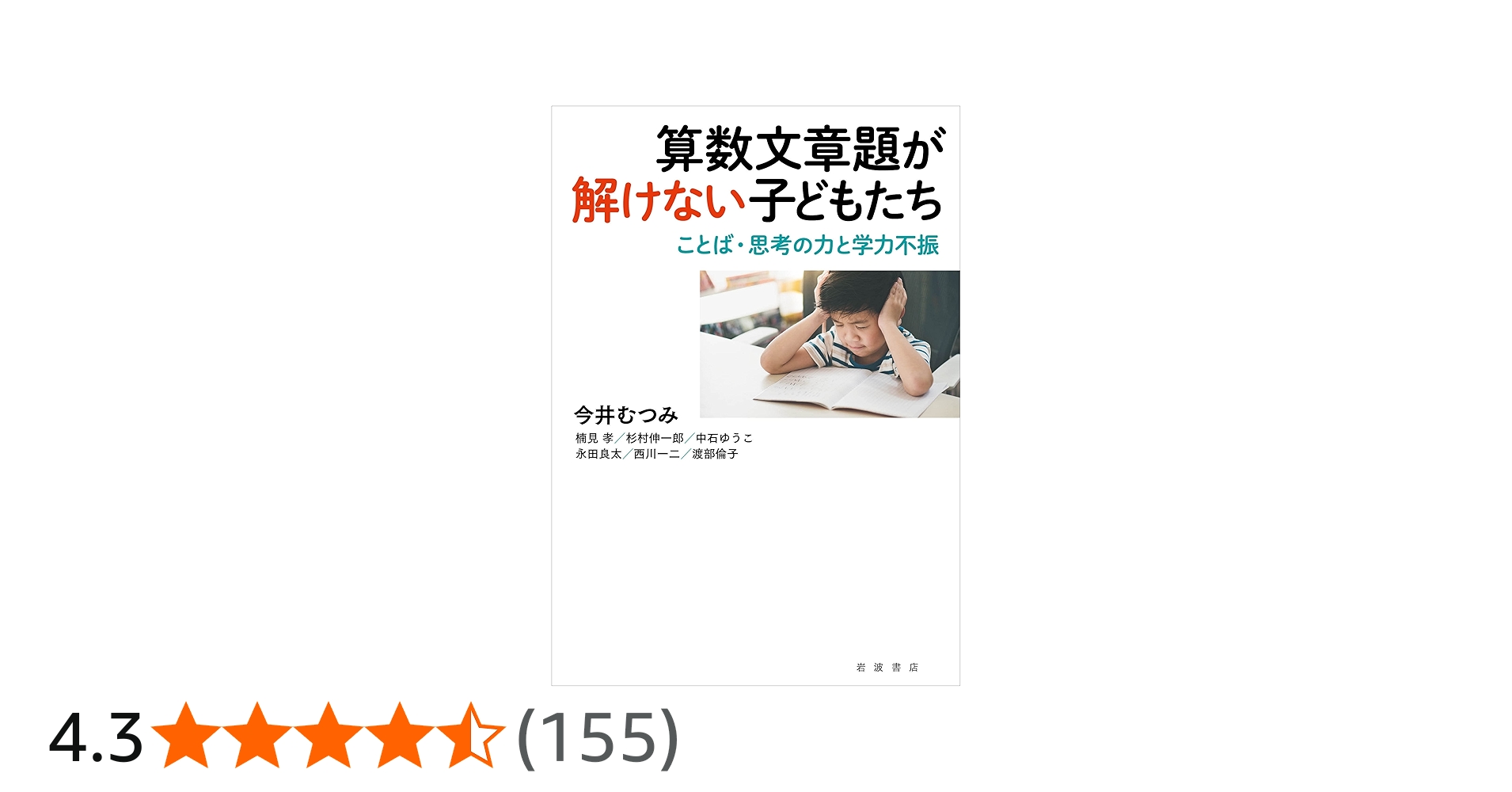
フォイヤーシュタイン・メソッドの話はいずれしていきますね。↓この本はフォイヤーシュタイン・メソッドの日本語訳された唯一の本です。ご興味のある方はぜひ!
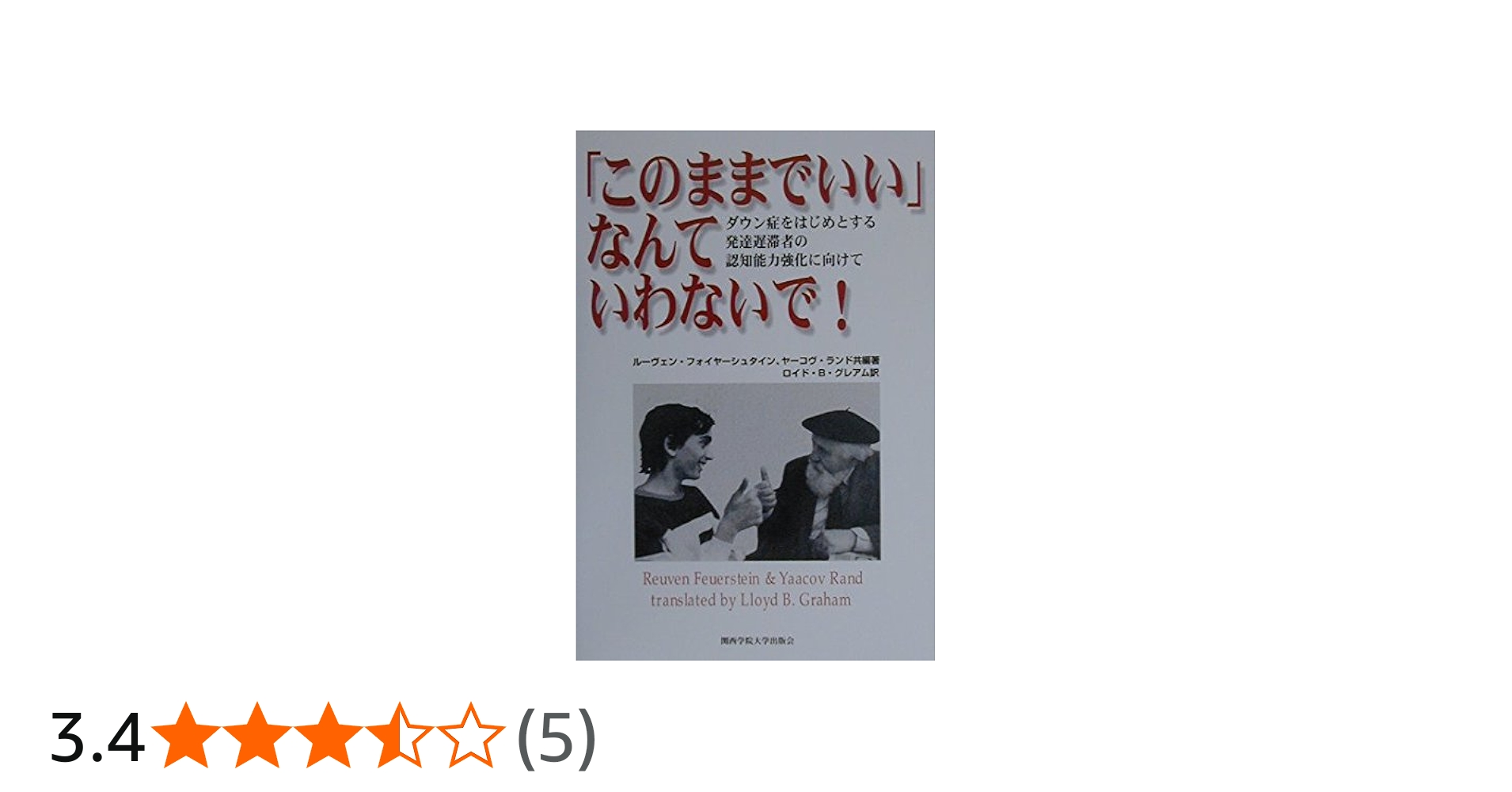
この本の中にもありますが、ルーヴェン・フォイヤーシュタイン博士は、「人の認知構造は変容可能である」それも「いつからでも」と言っています。つまり私たち大人も日々進化・変容しているということです。
これまで、「考える力のおはなし」の中で押さえるポイントをいくつかあげてきましたが、実はそのポイントを使って、大人も日々起きる問題を解決してます(あげているポイントは一部ですが・・)。なので、まずは私たち大人が「ほんまや〜」「同じようなことやってるねー」と気づくことが、子どもの考える力を伸ばし育むための役割となる早道と思っています。
職業柄、何事もフォイヤーシュタイン・メソッドの考えて分析してしまいがちな私は、みんとしょたうの読書会で気付いたことがあります。それを次回お伝えしたいと思います。

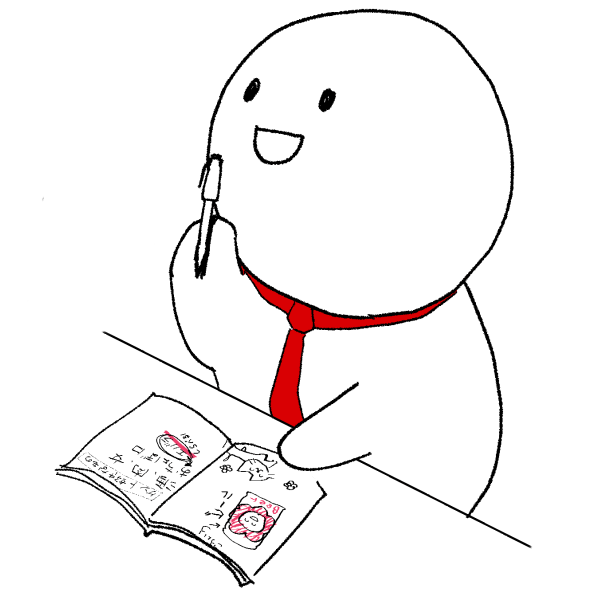


コメント