前回のおさらい

こんにちは。みどりです。
「ボールを遠くへ投げられるようになりたいんだ」という、我が子【うさぎ🐰】のつぶやきをもとに、「気づく」「意識する」「比べる」などについて考えてみるシリーズその2です。
前回の
「ボールを遠くへ投げられるようになりたいんだ。」その1
では、ボールを投げる動きの発達について主に触れました。
その中で
・自分はどうやっているのか?人はどうやっているのか?ということについてそれぞれ情報を集めていること
・「遠くに投げたい」という動機をもつ
とお話ししました。
今回は、その続きです。
比べるための情報収集
我が子【うさぎ🐰】は、自分がボールを投げる時の動きを客観的に捉え、友だちの動きと比べていました。
そして比べた結果、友だちと自分には違いがある💡(ʘ╻ʘ;)💡という気づきを得ています。
具体的には…
友だち…足→腰→背中→手 足からのパワーのつながりで遠くに投げることができている
自 分…足は一歩出している パワーのつながりは感じられない 手の振りだけで投げている
どちらも【ボールを投げる】という同じ行為をしているのですが、比べてみると実は【どのようにやっているか】と言う部分で違いがあるわけです。
比べることについて、詳しいことは
過去記事 「同じと違う」根拠をもって考える
を見ていただくといいかなと思います。

この情報収集について、どこで収集しているのかと言うと…
友だちの【投げる】については目から
自分の【投げる】については、筋肉や関節の感覚、手足の動きそのものから
主に情報を得ています。
目も手足も筋肉も関節も…すべて自分の身体です。
そういう意味で、どちらにしても自分の身体を使って情報収集していると言えます。
身体を使った情報収集
一説には、「人が得る情報のうち、8割が目から得ている」と言われたりしています。
無意識のうちに私たちは目からの情報にとっても頼っています。
私の好きなYouTubeのチャンネルで、面白いゲームをしていました(オモコロチャンネルって知ってます?絶対味覚王というシリーズです^ ^)。
ちょっと変わった味のお菓子をパッケージからから出して一つずつ食べ、何味のお菓子なのか当てるゲームです。
パッケージから出されているため、そのお菓子が何味なのか、味についての目で見る情報はありません。
6人くらいの人が一斉に同じ「グラタン味」のお菓子を食べて、「クラムチャウダー味」「クリームパスタ味」などと予想していました(*^^)
きっと最初にパッケージを見て、「これはグラタン味のお菓子」と分かった上で食べたら、全員「間違いなくこれはグラタン味」と思いながら食べることになったのではと思います。
目のように、ヒトが外の世界の情報を集めるために使う器官を「感覚器」といいます。
他に例えば、見えないところから呼ばれた際に声のする方に振り向くことができるのは耳が音をキャッチしているからですし、一口食べて「ちょっと傷んでるかも…」と判断がつくのは舌があるからです。
触れれば、見てなくても「これは〇〇だな」と想像できますし、床が傾いている家に立つとなんとなく気分が悪くなったりもします。
このように私たちは、いろんな感覚器で無意識のうちに情報を集め、それらを無意識のうちに処理しながら生活しています。
私たちが、運転しながら人と話したり、考え事をしながらタオルを畳んだりできるのは、無意識のうちに処理してくれる部分がしっかり働いているからです。
でも逆に、無意識だからこそうまくいかないこともあります。
「友だちは遠くにボールを投げることができるのに、自分は何でできないんだろう?さっぱりわからない!」
それは、【ボールを投げる】という行為をしていることはわかるけど、【どのようにやっているか】と言うところの情報をとらえられていない状態であるからと言えるでしょう。
無意識でしていることを、意識しながらやってみる
ではどうやったら、【どのようにやっているか】の情報を得やすくなるのでしょうか?
それは、ずばり
【意識上にあげてみる】。
先ほども少し触れましたが、私たちはいろいろな情報を無意識レベルで処理しながら生活しています。
歩く時にいちいち、右足をここに置いて体重移動して、それから左足を…なんてことは考えません。
でもタンスの角に小指をぶつけた途端、一番端っこの小さな部分ですら存在を意識することになります。

【うさぎ🐰】がしていたのは、ボールを投げる時の身体の動きを小さく分け、その小さなパーツごとに比べる、ということです。
それは顕微鏡の倍率を変えているようなものです。
大きく輪郭を捉えるならば、倍率は低く。
細かな部分まで捉えるならば、倍率は高く。
ずっと低い倍率のままでは、動きの細かな違いには気づきづらいですし、かといって高倍率のまま観察していても、細かすぎて動きの全体像は見えません。
大事なのは、必要に応じて適切に倍率を変えられるということです。
要するに【意識上にあげてみる】というのは、【自分で顕微鏡の倍率を変えながら観察する】とも言えるでしょう。
まとめ
【うさぎ🐰】が、友だちと自分の投げ方について情報を得たのは、「遠くに投げられるようになりたい」という動機があったからです。
動機があるからこそ、その動きや感覚自体に興味をもって観察することにつながりますよね。
「今のままでいい」「何も疑問がない」ならば、そもそも意識上にあがってくることはないのではないでしょうか。
とは言え、自分の動きそのものに目を向けて「どこを動かしているのか」「どんなふうに動かしているのか」と、観察して捉えることは、実は大人でも意外と難しいことです。
でも実は、まだ言葉を発しない赤ちゃんでもたくさんしているのです。
赤ちゃんは言葉ではなく、遊びの中で身体をたくさん動かして試行錯誤をする中で、動きや感覚そのもので捉えていっていると言われています。
ですから
○○ができるようになりたい…という動機をもったり、興味をもったりする
存分に・楽しみながら・失敗を恐れず・試行錯誤できる、環境や関係性を作る
ということが、大人も子どもも大事になるのではないかなと思います。
まずは、日常生活の中で
いつも無意識で、考えなくてもやっていることってなんだろう?
これをするときは、注意を向けながらやっているな。
を、それぞれ見つけてみるのも楽しそうですね^ ^


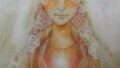
コメント